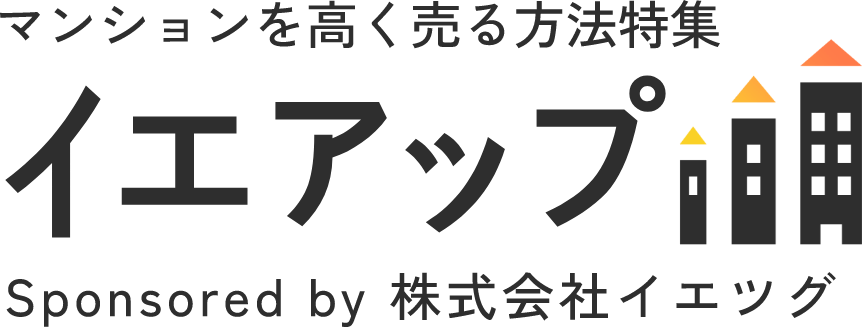マンション売却における確定申告の注意点
このサイトは株式会社イエツグをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
- 確定申告が「必要/不要」になる判断軸
- 譲渡所得の計算式・税率(長期/短期)・控除・特例
- 固定資産税等清算金や相続・共有など実務で迷いやすい論点
- e-Tax(スマホ申告)を含む申告の流れと必要書類一式
マンション売却で確定申告が必要か迷ったら、まずは本記事をご覧ください。
譲渡所得の計算式、長短期の税率、3,000万円特別控除や軽減税率などの特例、必要書類とe‑Taxの流れまで、国税庁情報を踏まえ分かりやすく整理しています。
申告不要/必要の判断軸や20万円ルール、相続・共有、固定資産税清算金の注意点や、実際の計算例も掲載!
マンション売却後の確定申告が「必要」になる条件とは
- 売却で利益(=譲渡所得)が出たら原則として確定申告が必要です。
計算式は譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)。
参照元:国税庁「土地や建物を売ったとき」 - 損失(マイナス)でも、マイホーム(居住用財産)の一定要件で損益通算・繰越控除などの特例を使う場合は申告が必要です。
参照元:タックスアンサー(譲渡所得) - 給与所得者の「20万円ルール」:
給与以外の所得(譲渡所得を含む)の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要(ただし住民税は別途手続きが必要な場合、かつ特例を使うなら申告必須)。
参照元:国税庁No.1900
譲渡所得の基礎:計算式と各要素の中身を知ろう
計算式の全体像
譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)
ただし、特例を使う場合はこの後に特別控除を差し引いて課税譲渡所得を算出します。
譲渡価額(収入に算入するもの)
- 売買代金のほか、未経過固定資産税・都市計画税の清算金を買主から受領した場合は収入金額(譲渡価額)に算入します。
参照元:国税庁 質疑応答事例
取得費(買ったときのコスト)
- 土地:購入代金+購入時諸費用等の合計。
- 建物:購入代金から減価償却費相当額を控除(非業務用):
取得価額×0.9×償却率×経過年数(※建物取得価額の95%が限度)。
なお、構造別の償却率(非業務用)は以下の通りです。
RC/SRC=0.015、木造=0.031、軽量鉄骨(3mm超4mm以下)=0.025 ほか
参照元:国税庁No.3261 - 取得費が不明な場合:概算取得費として、譲渡価額の5%を用いることができます。
参照元:国税庁No.3258
譲渡費用(売るために直接要した費用)
- 仲介手数料、測量費、印紙税、建物取壊し費用(更地売り)などが主な代表例です。
売却益への税率と所有期間の判定(長期/短期)
長期or短期の判定は、「売った年の1月1日現在」の所有期間で行い、5年超であれば長期、5年以下であれば短期となります。
いずれも分離課税で、住民税は別計算、所得税には復興特別所得税(2.1%)が上乗せされます。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期(5年超) | 15% | 5% |
| 短期(5年以下) | 30% | 9% |
なお、相続・贈与で取得した場合の所有期間の起算は、前所有者から通算します。これは長期/短期の判定や軽減税率の可否に影響します。
参照元:国税庁 質疑応答事例
譲渡所得と税額の計算を具体例で確認しよう
前提
- 売却価格:5,500万円
- 未経過固定資産税等清算金:6万円(収入に算入)
- 譲渡費用:174万円(仲介手数料171万円+印紙税3万円)
- 取得時:土地3,000万円、建物2,000万円(RC造、所有15年)
- 自己居住用・長期に該当
計算
- 譲渡価額=5,500+6=5,506万円
- 減価償却費=2,000×0.9×0.015×15=405万円(非業務用の式)
- 取得費=3,000+(2,000−405)=4,595万円
- 譲渡所得=5,506−(4,595+174)=737万円
- 概算税額(長期)
- 所得税:737×15%=110.55万円
- 復興特別所得税:110.55×2.1%=約2.32万円
- 住民税:737×5%=36.85万円
合計:約149.7万円(実効約20.315%)
※3,000万円特別控除などを使う場合は、先に譲渡所得から控除してから税率を適用します。
参照元:国税庁
マンション売却で使える主な特例(控除・軽減)
3,000万円特別控除(居住用財産)
自宅を売った場合、所有期間に関係なく最大3,000万円を譲渡所得から控除できます(要件あり・申告必須)。
参照元:国税庁No.3305
所有期間10年超の軽減税率
10年超保有の居住用財産は、(3,000万円控除適用後の)課税長期譲渡所得に対し、 6,000万円まで所得税10%・住民税4%、超過分は所得税15%・住民税5%(要件あり)。
参照元:国税庁No.3308
買換え(交換)による課税の繰延べ
売却前年〜翌年の3年内に要件を満たすマイホーム買換えをした場合、 譲渡益の課税を繰延べ可能(1億円以下・所有期間10年超・居住10年以上など)。3,000万円控除や軽減税率と選択適用。
参照元:国税庁No.3355
マイホームの譲渡損失:損益通算・繰越控除
要件を満たす場合、損益通算・翌3年繰越が可能(買換えの有無やローン残高の有無により要件が異なる/期限内申告+連続申告が条件)。
参照元:国税庁No.3390等
相続空き家の3,000万円控除
平成28年4月1日〜令和9年12月31日の売却で、要件を満たす被相続人居住用家屋(空き家等)に最大3,000万円(一定の場合2,000万円)の控除。
参照元:国税庁No.3306
なお、居住用特例(3,000万円控除・軽減税率・買換え)は、住宅ローン控除との時期的な併用制限があります。どれを選ぶかは節税効果で比較しましょう。
参照元:参考
共有名義・相続・清算金などはどうなるの?
- 共有名義:
持分ごとに計算・申告。3,000万円控除は共有者1人につき最大3,000万円(可否は共有者ごとに判定)。
参照元:国税庁 - 相続・贈与の所有期間:
前所有者の取得時期を通算して判定。
参照元:国税庁 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合 - 固定資産税等清算金:
売主が受け取る未経過分は収入金額へ算入。
参照元:国税庁 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
申告の締切・やり方(e-Tax含む)と必要書類
申告期間の目安
売却した翌年の2月中旬〜3月中旬(年により日付は前後)。
最新の情報は、国税庁特設サイトの確定申告特集(不動産売却)や スマホ申告案内で確認。
申告の流れ(標準)
- 1. 必要書類の収集
- 売買契約書(購入時/売却時)、領収書(仲介手数料・印紙税 等)
- 登記事項証明書、(住所と物件の所在地が異なる場合)住民票の除票/戸籍の附票 等
- 特例適用時の添付書類(住宅ローン残高証明書、耐震基準適合証明、市区町村の確認書、不動産番号の明細書 など)
- 2. 計算・書類作成
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)を作成。
参照元:国税庁 記載例 - 確定申告書(申告所得税・分離課税用)に転記。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)を作成。
- 3. 提出(e-Tax推奨)
- スマホ申告の手順/パソコンe-Tax/税務署へ持参または郵送
よくある質問(FAQ)
Q1. 管理費や修繕積立金の日割り清算は収入に入れますか?
未経過固定資産税等の清算金は収入に算入します。
管理費等の清算は契約実務・会計処理の整理が必要なため、契約書の記載に従い、税務判断は専門家へ相談してみましょう。
参照元:国税庁 質疑応答事例
Q2. 会社員で売却益がわずかです。申告は必要?
給与以外の所得の合計が20万円以下で特例を使わないなら、所得税の確定申告は不要(住民税は自治体に確認)です。
ただし、3,000万円控除など特例適用時は申告必須です。
参照元:国税庁No.1900
Q3. 相続で取得したマンションをすぐ売却した。期間の数え方は?
被相続人の取得時期を通算して所有期間を判定します。
参照元:国税庁 質疑応答事例
※本記事は国税庁公開情報をもとに一般的な取扱いを整理したものです。個別の事情(居住要件、区分所有、耐震基準、共有・相続関係、買換え計画など)で結論が変わることがあります。売却前後で税理士・仲介会社に書類を見せてご確認ください。
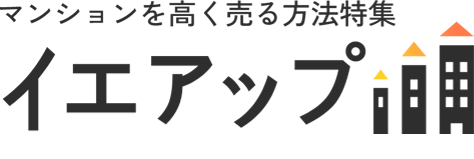
原則申告は必要!
減価償却や対応税率はケースバイケース
- 利益が出たら原則申告が必要です。損失でもマイホーム特例を使うなら申告必須となります。
- 取得費の減価償却(非業務用:取得×0.9×償却率×年数)と固定資産税等清算金の収入算入が計算式の基本。
- 税率は長期/短期で大きく変動します。長短の判定は売却年の1月1日現在から起算。なお相続・贈与は前所有者から通算して計算します。
- 3,000万円控除・軽減税率・買換え特例は強力ですが、住宅ローン控除との併用制限に注意しましょう。
- e-Tax(スマホ)でスムーズに申告できます。最新の手引き・記載例は国税庁などのサイトを確認してください。

最大限の利益獲得を支援
物件価格にかかわらず仲介手数料は約20万円(税込)で固定。売主の手取り額を最大化しつつ、広告・写真・販売戦略も一切妥協なし。費用を抑えて、しっかり売りたい方の強い味方です。